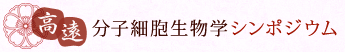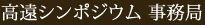- 高遠分子細胞生物学シンポジウム 【ホーム】
- 過去のシンポジウム
- 第24回高遠・分子細胞生物学シンポジウム
| タイトル | 第24回 高遠・分子細胞生物学シンポジウム |
|---|---|
| テーマ | 生命の制御系の進化を探る |
| 開催期間 | 2012年8月23日(木)~24日(金) |
| 開催場所 | 高遠さくらホテル |
2012年8月23-24日
- 植物の生存戦略を支える細胞内膜系
- 西村 いくこ [京都大学大学院 理学研究科 生物科学専攻]
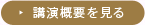
-
植物は静的な生物と思われがちです。しかし、細胞のなかは都市の道路のような忙しさです。これは原形質流動とよばれ、最も古い文献は、1774年のものとされていますが、その分子機構は200年来の謎です。私たちは、細胞内で最大の表面積をもつ小胞体の流動を見いだし、ミオシンXIモータによって駆動される小胞体運動が原形質流動の原動力である可能性が浮上してきました1。本シンポジウムでは、このような動的な植物細胞に親しんでもらった上で、小胞体や液胞などの細胞内膜系によって支えられる植物免疫機構を紹介します。
植物も動物と同様に常に様々な外敵にさらされながら生きていますが、動物にみられる免疫細胞のような特殊攻撃部隊をもたないため、植物は体中の全ての細胞あるいは組織がこのような外敵に立ち向かわなければなりません。いつ来るか分からない敵に対してどのようにして省エネ・省コストの防御を実現しているのでしょうか。植物は外敵から身を守るために、外敵の種類に応じて小胞体や液胞を巧みに利用していることが分かってきました。病害虫などの食害に対しては、酵素β-glucosidase 反応により忌避物質を生産します2。この酵素をもつ細胞は、地上部(葉)では植物のライフラインというべき葉脈(維管束)に沿って存在し、地下部(根)では表皮細胞に存在します。生存に必須な部位や外環境にさらされている部位にだけ防御システムを配備するという作戦です。
ウイルスや細菌に対しては、感染した細胞が病原体を巻き込みながら心中(過敏感細胞死)することにより、植物体は生き残ります。植物細胞は、液胞の中に多様な分解酵素や抗菌物質を大量に蓄積しています。ウイルスが感染すると、植物は液胞膜を崩壊させて、分解酵素を細胞質ゾルに放出し、ウイルスを直接攻撃すると同時に過敏感細胞死を起こします3。一方、細胞外で増殖する細菌に対しては、液胞と細胞膜を融合させ細胞内外をつなぐトンネルをつくり、液胞内部の抗菌物質を細胞外に放出して細菌を攻撃するとともに過敏感細胞死を起こします4,5。液胞は全ての植物細胞が持ちあわせているオルガネラであることを考えると、液胞膜崩壊や液胞膜—細胞膜融合の機構はコストをかけない植物の防御システムであると言えるかもしれません。最後に、病原菌の侵入口ともなる気孔の分化を制御する分泌ペプチドstomagen6にも触れたい。
文献
1. Ueda, H., Yokota, E., Kutsuna, N., Shimada, T., Tamura, K., Shimmen, T., Hasezawa, S., Dolja, V.V., and Hara-Nishimura, I. (2010) Myosin-dependent ER motility and F-actin organization in plant cells. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107: 6894-9899.
2. Yamada, K., Nagano, A.J., Nishina, M., Hara-Nishimura, I., and Nishimura, M. (2008) NAI2 is an endoplasmic reticulum body component that enables ER body formation in Arabidopsis thaliana. Plant Cell 20: 2529-2540.
3. Hatsugai, N., Kuroyanagi, M., Yamada, K., Meshi, T., Tsuda, S., Kondo, M., Nishimura, M., and Hara-Nishimura, I. (2004) A plant vacuolar protease, VPE, mediates virus induced hypersensitive cell death Science 305: 855-858.
4. Hatsugai, N., Iwasaki, S., Tamura, K., Kondo, M., Fuji, K., Ogasawara, K., Nishimura, M., and Hara-Nishimura, I. (2009) A novel membrane-fusion-mediated plant immunity against bacterial pathogens. Gene. Dev. 23: 2496-2506.
5. Hara-Nishimura, I., and Hatsugai, N. (2011) The role of vacuole in plant cell death. Cell Death Differ. 18: 1298-1304.
6. Sugano, S.S., Shimada, T., Imai, Y., Okawa, K., Tamai, A., Mori, M., and Hara-Nishimura, I. (2010) STOMAGEN positively regulates stomal density in Arabidopsis. Nature 463: 241-244.
- 遺伝暗号リプログラミングまでの歴史と展開
- 菅 裕明 [東京大学大学院 理学系研究科・化学専攻]
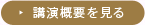
-
遺伝暗号は、全生命体で保存されている普遍的な「法律」である。1953年のDNA分子の発見から、わずか15年足らずで遺伝暗号が解読された偉業は、分子生物学に携わる研究者ならば誰もが興奮して学んだことだろう。それから50年経った21世紀、この遺伝暗号を自由にリプログラミングすることで、通常の蛋白質には含まれないアミノ酸を含んだ特殊なペプチド、擬天然物を自在に翻訳合成できる技術が完成した。この技術は講演者の菅が、化学と生物学の狭間で15年以上に渡って挑み続けた研究成果の集大成でもある。さらには、その技術を駆使した創薬すら達成されつつあり、生物学・医学への応用の可能性は無限にある。本講演では、その研究の歴史から最新技術の応用展開まで紹介する。
References
1) C. J. Hipolito, H. Suga “Ribosomal production and in vitro selection of natural product-like peptidomimetics: The FIT and RaPID systems” Current Opinion in Chemical Biology 16, 196-203 (2012).
2) J. Morimoto, Y. Hayashi, H. Suga “Discovery of macrocyclic peptides armed with a mechanism-based warhead that isoform-selectively inhibit a human deacetylase SIRT2” Angewandte Chemie International Edition 51, 3423-3427 (2012).
3) Y. Hayashi, J. Morimoto, H. Suga “In Vitro Selection of Anti-Akt2 Thioether-Macrocyclic Peptides Leading to Isoform- Selective Inhibitors” ACS Chemical Biology 7, 607-613 (2012).
4) Y. Yamagishi, I. Shoji, S. Miyagawa, T. Kawakami, T. Katoh, Y. Goto, H. Suga "Natural product-like macrocyclic N-methyl-peptide inhibitors against a ubiquitin ligase uncovered from a ribosome-expressed de novo library" Chemistry & Biology 18, 1562-1570 (2011).
5) K. Öjemalm, T. Higuchi, Y. Jiang, Ü. Langel, I. Nilsson, S.H. White, H. Suga, and G. von Heijne “Apolar surface area determines the efficiency of translocon-mediated membrane-protein integration into the endoplasmic reticulum” Pro. Nat. Acad. Sci. 108, E359-364 (2011).
6) Y. Goto, T. Katoh, H. Suga “Flexizymes for genetic code reprogramming” Nature Protocols 6, 779-790 (2011).
7) T. Kawakami, A. Ohta, M. Ohuchi, H. Ashigai, H. Murakami, H. Suga “Diverse backbone-cyclized peptides via codon reprogramming” Nature Chemical Biology 5, 888-890 (2009).
8) H. Xiao, H. Murakami, H. Suga, A. R. Ferre-D'Amare "Strcutural basis of specific tRNA aminoacylation by a small in vitro selected ribozyme" Nature 454, 358-361 (2008).
9) H. Murakami, A. Ohta, H. Ashigai, H. Suga "The fexizyme system: a highly flexible tRNA aminoacylation tool for the synthesis of nonnatural peptides" Nature Methods 3, 357-359 (2006).
- 遺伝子にコードされた分子スパイによる生命現象の解明に向けて
- 永井 健治 [大阪大学 産業科学研究所1)、JST さきがけ2)]
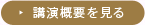
-
我々は、生体分子、細胞レベルの生命現象を研究対象として、遺伝子工学技術に基づく生体分子可視化技術を駆使して、個体の発生や刺激受容と応答に関わる分子間・細胞間相互作用を明らかにすることを大きな研究テーマに掲げている。個々の分子、個々の細胞のふるまいを生きた状態で可視化するのみならず、FRET などを利用した斥候分子を細胞内や組織内のあらゆる部位に放つことによって、細胞内シグナル伝達を可視化し、さらには操作する。このようなアプローチは、今後の生命科学研究の大きな流れとなるはずである。本セミナーでは細胞内の生体分子動態を定性的・定量的に可視化解析するための蛍光プローブと多色の励起・蛍光波長の観察を可能にする大口径白色光源リアルタイム共焦点顕微鏡、光遺伝学的ツールとの併用を可能にする超高性能自動発光プローブなどの紹介を中心に、細胞内生体分子の数・個性をターゲットとした「少数性生物学」という新しい学問領域の展望についても議論したい。
References
1) Chang YF et al. Optogenetic activation during detector “dead time” enables compatible real-time fluorescence imaging. Neurosci. Res. In press
2) Saito K et al. Conjugation of both on-axis and off-axis light in Nipkow disk confocal microscope to increase availability of incoherent light source. Cell Struct Func, 36, 237-246, 2011
3) Zhao Y et al. An expanded palette of genetically encoded Ca2+ indicators. Science, 333, 1888-1891, 2011.
4) Takemoto K et al. Chromophore-assisted light inactivation of HaloTag fusion proteins labeled with eosin in living cells. ACS Chem Biol 20, 401-406, 2011
5) Horikawa K et al. Spontaneous network activity visualized by ultra-sensitive Ca2+ indicators, yellow cameloen-Nano. Nature Methods 7, 729-732, 2010
- ゲノム倍化が引き起こす遺伝子発現調節機構の進化
- 荻野 肇 [奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科]
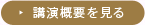
-
脊椎動物は進化の過程においてゲノム倍化を繰り返し経験してきた1。それに伴い祖先遺伝子から多くの重複遺伝子(パラログ)のペアが生まれ、さらにパラログペアの間で発現パターンが変化し、より複雑な遺伝子ネットワークが進化したと考えられている。しかし、具体的にどのようにシス調節配列が変化してパラログの発現の相違がもたらされたのか、未だ良くわかってはいない。
この問題に対して、我々はカンブリア紀に形成された3つのパラログ遺伝子、Pax2、Pax5、Pax8をモデルにアプローチしてきた。Pax2は眼や脊髄、脳、耳、腎臓など様々な組織で発現するのに対して、Pax5はこれらのうち脳だけで、Pax8は耳と腎臓だけでしか発現しない。ナメクジウオはゲノム倍化前に脊椎動物の祖先から分岐した種であり、3つの遺伝子に対する共通の祖先型オーソログPax2/5/8をもつ。Pax2/5/8の発現パターンがPax2とほぼ相同なことから、進化の過程でPax2が祖先型のシス調節を保持したのに対し、Pax5とPax8はシス調節を変化させたと予想される。
まず、比較ゲノムの手法とツメガエルの高効率トランスジェニックシステムを用いて2、Pax2とPax8のシス領域の網羅的解析をおこなった。その結果、祖先遺伝子由来のエンハンサーで、Pax2の発現する全ての組織で多面的な活性を示すものが、両者で保存されていることがわかった。しかしPax8はこの多面発現エンハンサーに加えて、発現を耳と腎臓に限局するための組織特異的なサイレンサーを持っていた。一方、ナメクジウオPax2/5/8のシス領域は、このようなサイレンサーを含まず、ツメガエルにおいてPax2の多面発現を再現した。したがって、ゲノム倍化後にPax8がサイレンサーを獲得したことが、Pax2とPax8の発現に相違をもたらしたと考えられる3。また、Pax5のシス領域にもPax2の多面発現エンハンサーと相同なエンハンサーが保存されていた。しかし、このエンハンサーは配列の部分変化のために通常は不活化されており、体液塩濃度が上昇したときだけ腎臓で活性化してPax5の発現誘導に働くことがわかった。
以上の結果は、パラログの進化におけるサイレンサーの獲得やエンハンサーの部分変化の重要性を示すと共に、遺伝子の発現パターンの大枠がカンブリア紀以前に確立されていたことを示唆している。
参考文献
1)Ohno, S. 1970. Evolution by Gene Duplication. Springer-Verlag, New York.
2)Ogino, H. & Ochi, H. 2009. Resources and transgenesis techniques for functional genomics in Xenopus.
Dev. Growth Differ., 51, 387-401.
3)Ochi, H., Tamai, T., Nagano, H., Kawaguchi, A., Sudou, N. & Ogino, H. 2012. Evolution of a tissue-specific
silencer underlies divergence in the expression of pax2 and pax8 paralogues. Nat. Commun., 3, 848.
- 幹細胞におけるヒストンH3リジン79(H3K79)メチル化の役割;アクセル?ブレーキ?
- 岡田 由紀 [東京大学分子細胞生物学研究所 病態発生制御研究分野 / さきがけ エピジェネティクス]
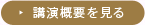
-
ヒストンH3の79番目のリジン残基(H3K79)のメチル化は、酵母からヒトまで広く保存されたヒスト ン修飾であり、ヒストンメチル化酵素 DOT1p/DOT1Lによってモノ・ジ・トリの全てのメチル化が付加される。H3K79メチル化は一般的に遺伝子の転写活性化と相関し、H3K4および H3K36のメチル化と協調して、高発現している遺伝子のコーディング領域に広範なピークを形成する。これはRNAポリメラーゼとの結合に依存するという報告もあるが、その分子機構は未だ明らかではなく、逆に細胞種によっては転写抑制やテロメアサイレンシングへの関与も報告されている。さらに酵母では、減数分裂やDNA傷害時の修復に重要であるとの報告もある1。
ここ数年、数種類の成人幹細胞で、H3K79メチル化による転写活性化が幹細胞性の維持に重要であるという報告がなされている2-4。一方で最近、H3K79メチル化の抑制が、線維芽細胞からのiPS化を促進するという、一見矛盾する報告がなされた5。実際DOT1L欠損ES細胞はaneuploidy等の異常を示すものの樹立・培養可能である6-7。従ってこれらの知見は、H3K79メチル化の役割が成人幹細胞と胎児幹細胞では異なることを示唆している。
我々のグループは生殖細胞特異的DOT1Lノックアウトマウスを樹立し、本ノックアウトマウスは胎児期精子幹細胞に由来する一過性の精子形成は正常であるが、その後成人精子幹細胞が維持・増殖できないために不妊になることを見出した。本シンポジウムでは、この研究成果をの紹介を中心に、これまでのDOT1Lと(幹)細胞に関する知見を総括して、H3K79メチル化の生理学的な役割について議論したい。
参考文献
1. Nguyen, A.T., and Zhang, Y. The diverse functions of Dot1 and H3K79 methylation. Genes Dev 25, 1345-1358
2. Nguyen, A.T., et al., DOT1L, the H3K79 methyltransferase, is required for MLL-AF9-mediated leukemogenesis. Blood 117, 6912-6922.
3. Jo, S.Y., et al., Requirement for Dot1l in murine postnatal hematopoiesis and leukemogenesis by MLL translocation. Blood 117, 4759-4768.
4. Lien, W.H., et al., Genome-wide maps of histone modifications unwind in vivo chromatin states of the hair follicle lineage. Cell Stem Cell 9, 219-232.
5. Onder, T.T., et al., Chromatin-modifying enzymes as modulators of reprogramming. Nature 483, 598-602.
6. Jones, B., et al., (2008). The histone H3K79 methyltransferase Dot1L is essential for mammalian development and heterochromatin structure. PLoS Genet 4, e1000190.
7. Barry, E.R., et al., (2009). ES cell cycle progression and differentiation require the action of the histone methyltransferase Dot1L. Stem Cells 27, 1538-1547.
- ミツバチの女王蜂分化誘導因子ロイヤラクチンの発見
- 鎌倉 昌樹 [富山県立大学 工学部 生物工学科]
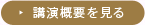
-
ミツバチは女王蜂と働き蜂からなる階級社会(カースト)を形成しており、同じ遺伝子型をもつ雌の幼虫のなかでも働き蜂の分泌するローヤルゼリー(RJ)を摂取した個体のみが女王蜂へと分化する。女王蜂は働き蜂に比べ、体サイズが1.5倍、寿命が20倍であり、1日に2000個の卵を産むという特徴をもっている。これまでにこの女王蜂への分化のしくみについてはまったく明らかになっていなかった。そこで筆者は、ミツバチの女王蜂への分化誘導機構の解明を試みた。
RJ中の女王蜂分化誘導因子を見出すためには、働き蜂の飼育系の構築が不可欠であったため、40℃で7日間、14日間、21日間、30日間保存したRJを作成し、それぞれのサンプルの女王蜂分化に対する影響を調べた。その結果、40℃で30日間保存したRJは完全な働き蜂
を誘導することが分かった。次に、新鮮なRJと40℃で30日間保存したRJとの間で成分組成の違いを調べ、さらに違いが見出された成分において女王蜂分化に対する影響を観察した結果、ロイヤラクチンと命名したタンパク質がRJ中の女王蜂分化誘導因子であることが明らかとなった1。
次に、ロイヤラクチンの女王蜂への分化誘導における作用機構について解析を行った。ミツバチには保存されている変異体がないため、ロイヤラクチンがカースト分化を誘導する分子メカニズムを個体レベルで詳細に解析することができない。そこで、発生生物学の研究でよく用いられ、多数の変異体が存在するショウジョウバエ(Drosophilamelanogaster) を女王蜂分化誘導機構の解析のためのモデル生物として使えないかと考え、ショウジョウバエに対するRJの影響を調べた。培地の組成の変化がショウジョウバエの表現型に及ぼす影響について検討した結果、ショウジョウバエの体サイズを増加させることのできるRJを含有する培地の組成をつきとめることに成功した1。さらに、RJの成分がショウジョウバエの表現型に及ぼす影響を検討した結果、ロイヤラクチンがショウジョウバエに対し女王蜂と同じような体サイズ、産卵数、寿命の増加を誘導することを明らかにした。このようなロイヤラクチンによる表現型の変化はロイヤラクチンをショウジョウバエの体内で過剰発現させた場合にもみられた1。
RJを含有する培地で種々のショウジョウバエ変異体を飼育し、ロイヤラクチンによるショウジョウバエの女王蜂様の表現型への変化に関与するシグナルについて調べた。その結果、ロイヤラクチンはこれまで生物個体の体サイズや寿命などの制御に中心的な役割を担っていることが知られているインスリン受容体ではなく、脂肪体(哺乳類の肝臓に相当)のEGF受容体(EGF:epidermalgrowthfactor,上皮成長因子)に作用しその下流シグナルを活性化させることによりショウジョウバエの体サイズ、産卵数、寿命を増加させていることがわかった1。このように、ショウジョウバエを用いた解析から明らかになったロイヤラクチンによる活性化シグナルが実際にミツバチの女王蜂への分化に関与しているかどうかを確認するため、ミツバチのRNAi試験を中心に詳細な解析を実施した。その結果、ショウジョウバエを対象とした解析結果と一致した結果が得られ、ミツバチにおいてもロイヤラクチンがEGF受容体シグナルを刺激して女王蜂への分化を誘導していることが明らかになった。ミツバチのカースト分化はハチの生態の根幹をなす現象であることから、今回の研究成果は、今後のミツバチの安定供給のための女王蜂の飼育法の開発やミツバチが突然失踪する現象(蜂群崩壊症候群)の解明につながるものと期待できる。
参考文献
1. Kamakura, M. Royalactin induces queen differentiation in honeybees. Nature 473, 478-483 (2011).
- 脊椎動物が季節を感知する仕組み
- 吉村 崇 [名古屋大学大学院 生命農学研究科]
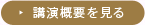
-
1920年代に生物が日照時間(日長)の変化をカレンダーとして利用し、様々な生理機能や行動の季節変化を制御していることが明らかにされ、光周性と名付けられた(1)。我々は洗練さ
れた季節適応能力を持つウズラをモデルとして、この仕組みの解明に取り組んできた。その結果、長日刺激によって視床下部内側基底部で甲状腺ホルモンの活性化酵素(DIO2)が発現誘導され、視床下部内で局所的に活性型甲状腺ホルモン(T3)が上昇することが、光周性の鍵を握っていることが明らかになった(2)。また、2004年にニワトリのゲノムが解読されたことをうけ、光周性を制御する遺伝子カスケードを明らかにすることを目的としてゲノムスケールの発現解析を行ったところ、下垂体隆起葉で合成される甲状腺刺激ホルモン(TSH)が「春告げホルモン」として視床下部内側基底部に作用し、DIO2が発現誘導されることが明らかになった(3)。我々はさらに、ウズラで明らかにした仕組みが哺乳類にもあてはまるか否かを検討するために、分子遺伝学が使えるマウスを用いて解析した。一般的にマウスは季節性を示さないと考えられていたが、遺伝子発現に着目するとマウスも日長の変化に反応することができ、TSHが日長の情報を仲介していることが明らかになった(4)。哺乳類においては眼が唯一の光受容器とされているが、その他の脊椎動物では脳深部に光受容器があるといわれていた。我々は最近、脳深部光受容器として新規光受容分子OPN5を同定した(5)。本講演では、脊椎動物が季節の変化を感知する仕組みについて紹介したい。
References
(1) Rowan W (1925) Relation of light to bird migration and developmental changes. Nature 115: 494-495.
(2) Yoshimura T, et al. (2003) Light-induced hormone conversion of T4 to T3 regulates photoperiodic response of gonads in birds. Nature 426: 178-181.
(3) Nakao N, et al. (2008) Thyrotrophin in the pars tuberalis triggers photoperiodic response. Nature 452: 317-322.
(4) Ono H, et al. (2008) Involvement of thyrotropin in photoperiodic signal transduction in mice. Proc Natl Acad Sci USA 105: 18238-18242.
(5) Nakane Y, et al. (2010) A mammalian neural tissue opsin (Opsin 5) is a deep brain photoreceptor in birds. Proc Natl Acad Sci USA 107: 15264-15268.
- 「母なる」細胞の染色体分配
- 北島 智也 [理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 染色体分配研究チーム]
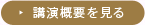
-
卵母細胞は、減数分裂により卵子を生み出し、受精を経て生体のすべての源となる「母なる」細胞です。卵母細胞は減数分裂のさい、染色体を正確に娘細胞に分配しなければなりません。もし染色体分配に誤りが起こると、その結果生まれた卵子が受精したとしても、それは流産やダウン症などの重篤な先天性疾患を引き起こします。卵母細胞においては、染色体は中心小体を含まない特別な紡錘体によって分配されることが知られていましたが、どのように正確な染色体分配が達成されるのか、その詳細は長年のあいだ謎に包まれてきました。
染色体を正しく分配するためには、分裂後期の前までにすべての染色体が安定な両方向性(染色体上の動原体ペアが紡錘体微小管によって両側へ引っ張られること)を確立しなくてはなりません。私たちは最近、マウス卵母細胞の減数第一分裂における染色体および動原体の動態を高解像度ライブイメージングし、完全な三次元の動原体トラッキングを初めて成功させました。このデータを網羅的かつ定量的に解析することで、以下の新しい知見を得ました。
減数第一分裂の前期において染色体は紡錘体の表面を移動し、赤道面上でベルト状の分布「前中期ベルト」を形成しました。その後、ベルト上の染色体のうちのいくつかが紡錘体の中心へと移動し、前中期ベルトを中期板へと変形させました。これと同時期に紡錘体は伸長して両極性紡錘体となり、また染色体上の動原体は紡錘体微小管によって引っ張られ始めました。しかしながら、最初の動原体と微小管の接続の90%近くは誤りを含んでおり、これらの染色体は平均2回の修正を経てようやく正しい安定な接続を確立していました。このことは染色体の両方向性の獲得は誤りがちなプロセスであることを示しており、卵母細胞で染色体分配が誤りやすいことと関係があるのかもしれません。
参考文献
Kitajima, T., S., Ohsugi, M., and Ellenberg, J.
Complete kinetochore tracking reveals error-prone homologous chromosome biorientation in mammalian oocytes.
Cell 146, 568-581(2011).
- 単純ヘルペスウイルスの感染・病態発現の分子基盤
- 川口 寧 [東京大学 医科学研究所 感染・免疫部門 ウイルス病態制御分野]
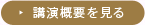
-
ヒトに感染するヘルペスウイルスは、現在までに8種類が同定されおり、各ウイルスは医学上重要な感染症を引き起こす。また、牡蠣や魚類、産業動物や伴侶動物においても、それぞれの種に固有なヘルペスウイルスが存在し宿主に様々な病気を引き起こすことから、ヘルペスウイルスは、医学、水産、畜産および獣医領域といった多領域において重要なウイルス群である。我々は、ヘルペスウイルスのプロトタイプであり、その研究成果が他のヘルペスウイルス研究に最も効率的にフィードバックされている単純ヘルペスウイルス(HSV)をモデルとし、ヘルペスウイルスの新しい感染制御法確立に向けての戦略的基礎研究を推進している。本シンポジウムでは、HSVの感染・病態発現の分子基盤に関して、我々がこれまでに明らかにしてきた知見を基に紹介する。
参考文献
1. J. Arii, H. Goto, T. Suenaga, M. Oyama, H. Kozuka-Hata, T. Imai, A. Minowa, H. Akashi, H. Arase, Y. Kawaoka, and Y. Kawaguchi.( 2010) Non-muscle myosin IIA is a functional entry receptor for herpes simplex virus 1. Nature 467: 859-862.
2. A. Kato, Z. Liu, A. Minowa, T. Imai, M. Tanaka, K. Sugimoto, Y. Nishiyama, J. Arii, and Y. Kawaguchi. (2011) Herpes Simplex Virus 1 Protein Kinase Us3 and Major Tegument Protein UL47 Reciprocally Regulate Their Subcellular Localization in Infected Cells. J. Virol. 85: 9599-9613.
3. M. Tanaka, A. Kato, Y. Satoh, T. Ide, K. Sagou, K. Kimura, H. Hasegawa and Y. Kawaguchi.(2012) Herpes Simplex Virus 1 VP22 Regulates Translocation of Multiple Viral and Cellular Proteins and Promotes Neurovirulence. J. Virol. 86: 5264-5277.
- 心臓の「生病老死」におけるWntシグナルの役割
- 内藤 篤彦 [大阪大学大学院 医学系研究科 心血管再生医学寄附講座 ]
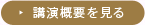
-
Wntシグナルは細胞の増殖、分化、移動を制御することで個体発生において重要な役割を果たしている。成熟した個体においてもWnt シグナルは生体の恒常性維持に重要な役割を果たしており、Wntシグナルの異常が様々な疾患の原因となることが知られている。
Wntシグナルが心臓発生においても重要な役割を果たしていることは初期胚を用いた数々の実験で証明されていたが、その作用について一定の見解は得られていなかった。私達はマウス幹細胞からの心筋細胞分化系を用いてWntシグナルが心臓発生・心筋細胞分化において時期特異的に二相性の役割を果たしていることを世界に先駆けて示し、一見矛盾しているように考えられた先の報告を説明するモデルを提唱した。また、心臓発生後期でWntシグナルを抑制することで心臓形成をサポートする因子としてIGF-binding protein-4 を同定した。現在は次世代シーケンサーを用いてWnt シグナルが期特異的な作用を発揮するメカニズムについて解析を行なっている。
近年、老齢マウスの血中にWntシグナルを活性化することで老化を誘導する物質が存在することが報告された(Science, 2007)。しかし、Wntタンパクは非常に疎水性が強く、血中に存在する可能性が低いことから、血中に存在する老化誘導物質はWnt活性化を持つ新たな物質である可能性が考えられた。我々は、加齢マウスの血液だけでなく、心不全モデルマウスの血液も強いWntシグナル活性化能をもつことを見出し、心不全モデルマウスの血液から新規Wnt シグナル活性化物質として補体分子C1qを同定した。C1qはWnt受容体であるFrizzledに結合後、C1r, C1sの活性化を介してWnt共受容体であるLRP5/6を切断することでWntシグナルを活性化した。
C1qおよびC1q発現は心不全モデルマウスの血中および心臓でそれぞれ亢進しており、心不全モデルマウスの心臓でWntシグナルの亢進を認め、また高血圧に伴う動脈リモデリングに動脈局所でのC1q発現亢進-Wntシグナル活性化が関与していることを見出している。心不全や高血圧症は老化が深く関与している疾患であり、現在老化および老化関連疾患(特に循環器疾患)におけるWntシグナルおよびC1q-Wnt経路の役割について解析を進めている。
- 個体発生と系統発生が示す新たな謎
- 入江 直樹 [理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 形態進化研究グループ]
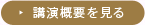
-
たったひとつの受精卵からはじまる動物の胚発生。ヒトの発生では、いきなりヒトのミニチュアができてそれが大きくなる訳ではなく、なんだか原始的な生物の姿を反映しながら形づくりが行われているようにもみえます。いまでも「胎児は、魚や両生類のように見える時期を経てヒトの形にだんだんと近づいていく」と表現されることもありますが、こうした進化と結びつけた仮説を作り上げたのが1800年代半ばのErnst Haeckel。胚発生は進化の早送りそのもの
である・・とするヘッケルの反復説、もちろん批判もあり修正は続きましたが、そのエッセンスは百数十年以上に渡り信じられてきました。ところが、気が付くと分子生物学全盛の現代科学にはそぐわない掴みどころのないお話。反論や別の仮説が提唱されるも観念論ばかりで、もはや取り残された分野として認識されていました。
それがここ数年で大きく変容しつつあります。最新の技術を手にした現代生物学者が分子レベルの研究からようやくこの諸問題に切り込むことに成功し、発生砂時計モデルという仮説の妥当性を示しはじめました。
ようやく遅れを取り戻しはじめた進化と発生の問題。しかし、すっきりと問題が解けたかと思いきや、実は現代発生生物学者の直感とはやや違った理解を支持するものでした。我々が知る「カスケード状に情報を増幅する分子発生プログラム」という理解から推測される進化的多様性とは大きく異なり、初期胚は意外にも進化的変化を許容してしまうことを示していたのです。ビルに例えると下層階が揺れても中層階は揺れないといったイメージで、いかにも生物らしいやわらかさを伺わせます。当日は進化生物学が教えてくれた発生現象の謎について広く議論できれば幸いです。
References
1. Irie, N., Sehara-Fujisawa, A., BMC Biology, 5:1, 12 January 2007
2. Irie, N., Kuratani S., Nature Communications, 2 : 248., 2011