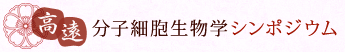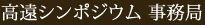- 高遠分子細胞生物学シンポジウム 【ホーム】
- 過去のシンポジウム
- 第31回高遠・分子細胞生物学シンポジウム
| タイトル | 第31回 高遠・分子細胞生物学シンポジウム |
|---|---|
| テーマ | 微生物・植物・動物・ヒトをつらぬくバイオロジー |
| 開催期間 | 2019年8月22日(木)~23日(金) |
| 開催場所 | 高遠さくらホテル
https://www.ina-city-kankou.co.jp/sakurahotel/ 〒396-0214 長野県伊那市高遠町勝間217番地 TEL.0265-94-2200 |
2019年8月22日-23日
- 森林の開花季節を遺伝子発現から知る
- 佐竹 暁子 [九州大学大学院 理学研究院 生物科学部門]
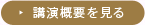
-
桜は春に咲き、トノサマガエルは初夏に産卵し、どんぐりは秋に実るように、四季の明瞭な地域では生物は種毎に決まった季節に繁殖を行う。このような生物の季節的活動をフェノロジーと呼ぶ。赤道付近に位置する熱帯雨林は、日本のように四季の明瞭な地域とは異なり年中湿潤で環境の変化が小さいにも関わらず、フタバガキ科に代表される東南アジアの植物はなんらかの環境シグナルを手がかりとして数年に一度100種を超える植物が一斉に同調して開花し子孫を残す。熱帯雨林でみられるこの壮大な一斉開花を引き起こす環境シグナルは何かについて1980年代より盛んに議論がなされてきたものの、長い間解決されないままであった。一斉開花でみられるような繁殖フェノロジーの年変動は、冷温帯林を優占するブナや照葉樹林の主要樹種であるカシやシイ類にも見られ、古くから豊凶現象として知られていた。しかし花量や種子量の年変動が生じるメカニズムについては、多くの仮説が提案されてきたものの変動を生み出す原因となる環境応答性については未解明のままであった。
私達は、長年謎とされてきた一斉開花および豊凶現象のメカニズムを解き明かすことを目標に研究を推進してきた。私達の研究方法の特徴は、生物の環境応答にみられる多様性を相同遺伝子というゲノム上の共通性と数理モデルによって記述される環境応答ロジックの共通性をもとに明らかしようとする点である。植物が開花に至る背後には、長い進化の過程で形作られた緻密な遺伝子制御ネットワークが存在する。それは日の長さや温度そして栄養状態などの環境が整ったタイミングで花組織を形作る遺伝子群を発現させ、開花を誘導することに役立っている。本講演では、生活史と生息環境の異なる植物を対象に遺伝子発現を野外でモニタリングし観測データを数理モデルと融合させることによって、数年に一度大規模に開花・結実する一斉開花現象やブナ林の豊凶現象の仕組みを解き明かした成果を発表する。現在伐採などで規模が縮小されている熱帯生態系や地球環境変動に直面する森林生態系の将来を予測するアプローチについても紹介したい。
参考文献
1. 佐竹暁子, 沼田真也, 谷尚樹, 市栄智明(2016)一斉開花:多様な種が同調して刻む繁殖リズム 新田梢、陶山佳久編「生物リズムの生態学 時をはかる生物たちの多様性」文一総合出版, 東京
2. 佐竹暁子 (2016) 数理モデルを通してみる植物の環境応答力, 化学と生物, 54, 205–211.
- 昆虫の多様な形質をもたらす分子メカニズムを探る
- 新美 輝幸 [基礎生物学研究所 進化発生研究部門/総合研究大学院大学 生命科学研究科]
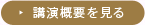
-
昆虫は、全生物種の約50%、全動物種の約75%を占めるほど種数が多い生物群であることから、この地球上で最も繁栄した生物であると考えられています。豊富な種数を誇る昆虫の様々な形質は、多様性に富んでいます。近年の次世代シークエンサー技術やゲノム編集技術の登場により、魅力的な形質を有する非モデル昆虫にも分子遺伝学のメスを入れることが可能となってきました。そこで私たちは、これら解析技術を駆使することで、新奇形質の形成に関与する遺伝子を特定し、その形質の多様化をもたらす分子メカニズムの解明に取り組んでいます。近年私たちは、興味深い生命現象を有するものの、これまであまり研究されることがなかったテントウムシやカブトムシなどの非モデル昆虫を研究材料に、その新奇形質形成の一端を明らかにすることに成功しました。
テントウムシは主に赤色と黒色からなる目立つ斑紋をもっています。この斑紋は、種に特徴的なパターンを示し、近縁種間でも異なっています。興味深いことに、ナミテントウには種内において極めて多様性に富む斑紋多型が存在します。一方、カブトムシの角は性的二型形質であり、雄だけに形成されます。角は近縁種間において数や形、大きさ、形成される場所などの点で多様性に富んでいます。テントウムシの斑紋やカブトムシの角の多様性はどのような分子メカニズムによってもたらされるのでしょうか?本シンポジウムでは、テントウムシの翅の斑紋形成とカブトムシの角形成の分子基盤に関する研究成果および今後の展望について紹介します。
参考文献
Ando, T., Matsuda, T., Goto, K., Hara, K., Ito, A., Hirata, J., Yatomi, J., Kajitani, R., Okuno, M., Yamaguchi, K., Kobayashi, M., Takano, T., Minakuchi, Y., Seki, M., Suzuki, Y., Yano, K., Itoh, T., Shigenobu, S., Toyoda, A. and Niimi, T. (2018) Repeated inversions within a pannier intron drive diversification of intraspecific colour patterns of ladybird beetles. Nature Communications, 9, 3843.
Ohde, T., Morita, S., Shigenobu, S., Morita, J., Mizutani, T., Gotoh, H., Zinna, R. A., Nakata, M., Ito, Y., Wada, K., Kitano, Y., Yuzaki, K., Toga, K., Mase, M., Kadota, K., Rushe, J., Lavine, L. C., Emlen, D. J., Niimi, T. (2018) Rhinoceros beetle horn development reveals deep parallels with dung beetles. PLOS Genetics, 14, e1007651.
Morita, S., Ando, T., Maeno, A., Mizutani, T., Mase, M., Shigenobu, S. and Niimi, T. (2019) Precise staging of beetle horn formation in Trypoxylus dichotomus reveals the pleiotropic roles of doublesex depending on the spatiotemporal developmental contexts. PLOS Genetics, in press.
- DNAイベントレコーディング
- 谷内江 望 [東京大学先端科学技術研究センター]
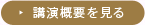
-
全ての生命システムは進展し、向上性を維持する複雑な細胞群から構成される。これを理解することが重要になっている生物学の課題は枚挙にいとまがないが、現在の生物学のアプローチには様々な制約がある。例えば、薬剤環境下において悪性腫瘍から耐性を示す細胞クローンが得られたとき、そのクローンの持つトランスクリプトームは調べることができても、同じクローンが薬剤暴露前の集団でどのような状態にあったのか解析することは1細胞トランスクリプトーム技術をもちいても難しい。また哺乳動物の発生も、受精卵から胚盤胞程度までの段階については細胞分裂を顕微鏡下で観察することができるが、全身を形成する細胞系譜の全容は明らかではない。一見当たり前のようであるが、これらの解析が難しい本質的な理由は「自然科学において、私達は目の前に現存する試料しか解析できない」ということである。私達はタイムトラベルができない。細胞をすり潰さないと高解像度の分子プロファイル情報は得られないし、システムを生きたままにして時系列で解析すると限られた情報しか得られない。様々な生命システムにおいて、それを構成する細胞群が時間経過とともにどのように分子プロファイルを変えながら進展していくのか知ることは極めて難しい。私達のチームではDNAをメモリデバイスと捉え、細胞内で人工DNAのデジタル配列に分子あるいは細胞の状態を経時的に記録していけば、任意の時刻に観察したシステムについてその過去を含めた状態情報を取り出すことができると考えている。この基本概念に基づいて、本会でははじめにタンパク質間の相互作用状態に応じて変化するDNA配列をもちいてタンパク質インタラクトームを一斉に計測する技術を紹介する。続いて、悪性腫瘍やラボ内進化実験における細胞クローンの経時的な計測技術、哺乳動物の発生における細胞系譜の丸ごとトレーシング法、これらのための新しいゲノム編集技術群の開発状況を報告する。
- がん微小環境の免疫抑制ネットワークとがん免疫療法
- 西川 博嘉 [国立がん研究センター研究所 腫瘍免疫研究分野・先端医療開発センター 免疫 TR分野/名古屋大学大学院医学系研究科 微生物・免疫学講座 分子細胞免疫学]
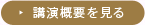
-
Cancer Immunoeditingに従えば、がんは免疫系からの攻撃を受けにくい免疫原性の低いがん細胞を選択するとともに、様々な免疫抑制機構を用いて免疫系から逃避することで、臨床的「がん」となる。現行の免疫チェックポイント阻害剤(ICB)で臨床効果が認められるのは、免疫選択が不十分ながらPD-1などによる免疫抑制により発がんした炎症性がんである。一方、EGFR変異非小細胞肺癌(NSCLC)では、ICBの治療効果が低いことが示されている。EGFR変異NSCLCは、EGFR野生型NSCLCに比較して遺伝子変異数が少なく、がん微小環境の炎症反応が低いこと一つの要因と考えられた。さらに興味深いことに、非炎症性がんであるにも関わらずEGFR変異NSCLCでは、制御性T細胞浸潤(通常は炎症性がんで浸潤が多い)が多く認められたため、EGFRシグナルが免疫系に及ぼす影響を検討した。EGFRシグナルは、ケモカイン転写調節により直接的にCD8+T細胞浸潤を阻害し、制御性T細胞浸潤をがん局所に誘導していた。EGFR変異腫瘍マウスモデルを用いて検討したところ、EGFRシグナル阻害剤とPD-1阻害剤の併用は単剤に比較して有意に抗腫瘍効果が向上した。
これらの併用療法が進められることで、免疫関連有害事象(irAE)が問題となる。irAEにはステロイド剤が多く用いられるが、ステロイド剤のICBによる抗腫瘍効果に与える影響は不明であった。マウスモデルを用いて検討したところ、ステロイド剤はがん抗原特異的CD8+T細胞のプライミングを阻害するものの、活性化されたがん抗原特異的CD8+T細胞については影響を与えないことが示された。さらに重要なことに、ICBによる長期予後に関与するメモリーT細胞形成において、ステロイド剤はTCR親和性が低い自己抗原特異的CD8+T細胞を選択的に抑制していた。これらの抑制は、TCR下流シグナルによるステロイド受容体のリン酸化調節により、メモリーT細胞に重要な脂肪酸代謝に影響を与えていることが重要であることが明らかになった。
今後は、がん患者のがん細胞の特性をゲノム解析により明らかにするとともに、がん局所での免疫応答を統合的に検討することで、個々の患者のがん微小環境に十分に配慮した治療開発「免疫プレシジョン医療」が枢要である。
- 細胞内でゲノムはどのような構造で収納されているか?
- 谷口 雄一 [理化学研究所 生命機能科学研究センター]
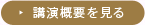
-
生命を構成するための源となるゲノムDNAは、4つの塩基:アデニン、チミン、グアニン、シトシンからなる1次元配列情報で構成されています。
しかし、実際の細胞の中にゲノムDNAがどのような3次元構造で収納されているのかは、これまでの研究ではあまり詳細には分かっていませんでした。
そこで我々は、ゲノムの最小構造単位である単一ヌクレオソームレベルの分解能で、ゲノムの3次元構造を決定する手法を開発しました[1,2]。この解析法は、従来の次世代シーケンサーを用いたゲノム構造解析法を高分解能化するのと同時に、分子動力学計算による3次元分子モデリングをスーパーコンピューターを用いて大規模に行うことにより初めて実現されました。この技術を用いて出芽酵母のゲノムを解析したところ、これまで規則的に並んでいると考えられていたヌクレオソーム配列が、実は2通りのヌクレオソーム配列(正四面体型とひし形型)の組み合わせによって成り立っていることを見つけました。
今後、ヒトを含む様々な生物種に解析を拡張し、疾患や薬剤存在下におけるゲノム構造を解析することにより、ゲノムDNAの収納原理の一般則や、ゲノム構造による細胞状態の制御論理が明らかになってくると期待されます。
[1] Ohno, M., et al., Cell 176, 520-534 (2019)
[2] 理研・JST合同プレスリリース「世界最高分解能で全ゲノムの3次元構造を解明-ゲノムの基本構造単位の発見-」2019年1月18日
- 階層をつなぐ視点からダイナミクスを考える。
- 澤井 哲 [東京大学大学院総合文化研究科 広域科学専攻相関基礎科学系]
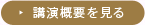
-
生命にはその部品の設計図はあっても、システム全体の動作についてのはっきりした設計図は見当たりません。細胞運動の素過程は、酵素反応や、重合反応などに還元されますが、それらがいかに組み合わせって、複雑で巧みな細胞運動や形状の特徴が出現するのでしょうか。また、細胞の動きは単純であっても、それらがくみあわさることで、いかにして細胞の配置がきまり、組織レベルのパターンが出現するのでしょうか。細胞性粘菌Dictyostelium discoideumは単細胞生物でありながら、栄養が不足すると、多数の細胞が集合し、それらが分化して子実体を作ることで知られ、単細胞から多細胞生物へ至る道を理解する上で注目すべき生物種です。多数の粘菌細胞からcAMPが周期的に放出され、その濃淡が、波を作り、それをもとに集合し、数種類の細胞型へと分化し、細胞が再配置されて子実体を形成します。粘菌にみられる現象は飢餓を克服して胞子を作るための仕組みであり、生物学として重要なものですが、一方で、高等動物では測定しにくい、組織内の細胞運動をともなった現象などの問題にとっての、モデル生物系としての特色があります。本講演では、1)細胞集団の秩序を決定する「場」はいかに自己組織化するのか、2)細胞はいかに移動方向を決定しているのか?3)動く細胞の形状はいかに決定しているのか?について、私達が粘菌から学んだことを時間の許す範囲で紹介し、その示唆するところを参加者と議論する。
文献
1. T. Fujimori, A. Nakajima, N. Shimada, S. Sawai (2019) Tissue self-organization based on collective cell migration by contact activation of locomotion and chemotaxis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 116, 4291-4296.
2. K. Kamino, Y. Kondo, A. Nakajima, M. Honda-Kitahara, K. Kaneko, S. Sawai (2017) Fold-change detection and scale-invariance of cell-cell signaling in social amoeba. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 114, E4149-E4157.
3. A. Nakajima, S. Ishihara, D. Imoto and S. Sawai (2014) Rectified directional sensing in long-range cell migration. Nat. Commun. 5, 5367.
4. D. Taniguchi‡, S. Ishihara‡, T. Oonuki, M. Honda-Kitahara, K. Kaneko and S. Sawai (2013) Phase geometries of two-dimensional excitable waves govern self-organized morphodynamics of amoeboid cells. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 110, 5016-5021. (‡ Equal contribution)
5. T. Gregor, K. Fujimoto, N. Masaki and S. Sawai (2010) The onset of collective behavior in social amoebae. Science 328, 1021-1025.
6. S. Sawai, P.T. Thomason and E.C. Cox (2005) An autoregulatory circuit for long-range self-organization in Dictyostelium cell populations. Nature 433, 323-326.
- 腸管恒常性の維持機構
- 竹田 潔 [大阪大学大学院医学系研究科・免疫学フロンティア研究センター]
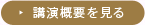
-
口から始まり肛門で終わる消化管は、摂取する食事成分を消化し、栄養分を作り出し、それを吸収する臓器である。栄養分の吸収を司る臓器である消化管、特に小腸、大腸は、表面積がテニスコート1.5面分にも相当する広大な臓器であるとともに、免疫細胞が人体で最大数存在している組織である。この臓器は極めてユニークで、口から摂取する食事成分だけでなく、腸内細菌という異物が多数存在している。免疫系は、細菌などの異物を非自己として認識し排除するシステムであるが、消化管では免疫細胞が最大数存在しているにも関わらず、腸内細菌に対して反応をすることなく、腸管の恒常性が維持されているのである。このバランスが崩れて、腸管の免疫系が腸内細菌を攻撃することにより、クローン病、潰瘍性大腸炎に代表される炎症性腸疾患が発症する。炎症性腸疾患は、近年我が国で患者数が急増している難治性の疾患である。私たちは、腸管の免疫系の活性制御機構および腸管上皮による腸内細菌の宿主侵入抑制機構などに着目し、腸管の恒常性維持機構をマウスモデルおよびヒトの炎症性腸疾患も対象として解析している。
そして、腸管組織の免疫細胞は他の組織の免疫系と異なり、その活性が抑制(制御)されていること、炎症性腸疾患患者ではその活性制御機構が障害されていることを見出してきている。また、腸内細菌が免疫系に晒されないメカニズムとして、腸管上皮細胞が産生する分子(Lypd8)による新規バリアメカニズムを明らかにしてきている。Lypd8などによる分子により直接宿主細胞と接することなく腸管腔内に棲息している腸内細菌が宿主に作用するメカニズムとして、腸内細菌叢依存性に腸管腔内で産生される分子の宿主作用機構についても解析している。その結果、アデノシン3リン酸、分子鎖アミノ酸、二次胆汁酸、乳酸、ピルビン酸などの宿主細胞への作用機構を明らかにしてきた。
このように、腸管の恒常性は、腸内細菌と免疫系の相互作用、そしてその制御により、見事なまでに維持されている。
References
Morita N, et al. Nature 566,110-114 (2019).
Okumura R, et al. Nature 532, 117-121 (2016).
Kitada S, et al. J. Exp. Med. 214, 1313-1331 (2017).
Tsai SH, et al. Immunity 42, 279-293 (2015).
Atarashi K, et al. Nature 455, 808-812 (2008).